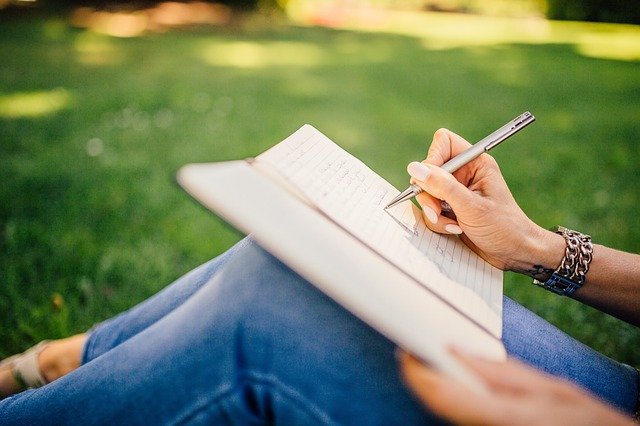こんにちは。
この記事に興味を持ってくださりありがとうございます。
この記事を見に来てくれた方は、TOEICに興味があったり、
TOEICを受ける予定がある方だと思います。
TOIECはビジネスシーンでは必須の英語スキルになっていて、
一番メジャーな英語力の指標です!
ですが、初めて受験される方は、
TOEICがどんな試験なのかも、
どのように勉強したらいいのかも分からないですよね?
この記事はそんな方にTOEICの試験の特徴と、
対策のポイントをまとめました。
TOEICをこれから受けるという方も、
勉強方法がイマイチ分からないという方も
是非参考にしてください!
この記事を書いた人

りょうた(ブログ管理人)。会社員。
理系の大学院卒。メーカー勤務。
入社後、英語学習を開始。TOEIC 900(2022.1)
パート別の特徴と対策

はじめに、各パートの特徴と一般的な対策を
簡単に紹介したいと思います。
各パート、後で丁寧に説明します!
| Part 1 【設問特徴】 ・写真を英文で説明し、最も適切な説明を選ぶ 【対策】 ・身の回りの写真を見て英語で説明する。 ・問題のスクリプトを見て写真を思い浮かべる。 ・分からない単語を覚える。 |
| Part 2 【設問特徴】 ・会話の設問に最も合う回答を選ぶ 【対策】 ・シャドーイングなど |
| Part 3 【設問特徴】 ・会話を聴いて、設問に答える。 【対策】 ・スクリプトの精読 ・シャドーイングなど |
| Part 4 【設問特徴】 ・スピーチを聴いて、設問に答える。 【対策】 ・スクリプトの精読 ・シャドーイングなど |
| Part 5 【設問特徴】 ・短文の穴埋め問題 【対策】 ・Part 5対策テキストを使った問題演習 |
| Part 6 【設問特徴】 ・長文の穴埋め問題 【対策】 ・スクリプトの精読 ・速読など |
| Part 7 【設問特徴】 ・長文を読んで設問に答える 【対策】 ・スクリプトの精読 ・速読など |
それでは、次に、もう少し詳しく紹介したいと思います!
Part 1(特徴と対策)
Part 1は写真を英語で正しく説明している英文を選ぶ問題です。

たとえば、この写真だったら、
「男性が手押し車を使っている」
みたいな説明が流れます。
誤答の説明は写真と全然関係のない説明をすることがおおいので、
難しい問題もありますが、
点数が取りやすいパートです。
ですが、単語に関しては知らないとアウトです。
そして、なぜかPart 1は変わった単語が出てくるというのも特徴です。
手押し車wheelbarrow
道具(楽器)insturment
看板billboard
掲示板bulletin board
など、他のパートとは傾向が異なります。
単語で難度を上げているけれど、
極端に難しい単語を使っているわけでもない
という独特のラインを狙って問題を作成しているのかな?
と私は思っています。

では、Part 1の対策ですが、
シンプルに単語を覚えましょう。
TOEIC用の単語集であれば必要な単語は基本的に載っています。
金フレはPart 1に出てくることが、
ちょっと解説されていたりします。
次に写真を見て英語で説明する文章を考えたり、
音声のスクリプトを見て写真を思い浮かべると言ったトレーニングがおススメです。
最後に、音声を直ぐ後から繰り返すシャドーイング、
音声に合わせて音読をするオーバーラッピング
などのようなトレーニングをするとよいと思います。
また、聴いた音声を書き留めるディクテーション
もオススメですが、
これは時間がかかりすぎるというデメリットもあるので、
時間がかかっても、ちゃんと英語力をつけていきたい
という方にはおすすめしますが、
短期集中でTOEICに取り組んでいる方は必要ないと思います。
一般的にはリスニング力を高めるには
シャドーイングが特におすすめと言われ、
オーバーラッピングで読む力が付きます。
Part 1のまとめ
- Part 1は単語に注意!
- 模試を使ってシャドーイングをしよう。
Part 2(特徴と対策)
続いてPart 2に行きます。
Part 2は会話の回答を3つの中から推測する問題です。
例えば、
「受け付けはどちらですか?」
という質問であれば、
「廊下をまっすぐ進むと右手にあります」
みたいなイメージです。
Part 2の特徴としては、
回答で話をそらすようなパターンがあることです。
例えば、同じ質問を例にすると、
「受け付けはどちらですか?」という質問に、
「私はこちらの社員ではありません」
が回答になることもあるということです。
また、話をそらすときに特に多いのですが、
回りくどい説明で難度を上げてくることがあります。
Part 2はポイントとして次の2点を覚えておくととても有効です。
1つ目は問題文の文頭に特に集中することです。
When、Where、What、Who、Whoseなどの
5W1Hを聴き分けるのが難しいのですが、
これは必須です。
また、Yes、Noで答える問題なら、
どの助動詞(Do、Did、Does、Can、Will、Haveなど)
またはBe動詞を使用したかの聴き分けが必要です。
これがかなり難しいので、しっかりとスクリプトを見ながら、
どのように発音しているのかを頭に叩き込みましょう!
2つ目は回答に似た音が出てきたらひっかけということです。
例えば、「コピー機が故障しました」という問題文の回答に
「コーヒーを1つ下さい」みたいな
似た音が選択肢に含まれることがあります。
これを知っていると、
似ている発音が出てきたら、
「ひっかけだから、答えじゃないな!」
と選択肢から外すことができます。
また、他のパートは全て4択なのですが、
なぜかPart 2だけ3択ですので、消去法が有効です。
1つでも明らかに違うことが分かれば、
2択なので分からなくても50%も正答できるのです。

Part 2対策は、Part 1と同じように、
模試などの問題を使って
シャドーイング、オーバーラッピングなどを行いましょう!
回答のうち誤答となる2つは飛ばして、
問題文と正答のみを学習しても大丈夫です。
高得点を狙う方は全て聴き取るトレーニングが重要ですが、
初めは問題文と正答の対を意識して学習しましょう。
また、特に問題文の方を重点的に学習することを意識すると良いと思います。
Part 2まとめ
- シャドーイングなどで繰り返し学習しよう。
- 問題と正答の対で学習しよう。
- 特に冒頭、集中して聴き取ろう!
Part 3, 4(特徴と対策)
次はPart 3、4です。
この2つのパートの違いは、
Part 3が2人か3人の会話、
Part 4は1人のスピーチになります。
どちらも会話またはスピーチを聴いて、
3つの設問に回答する問題です。
Part 3は13題×3問の計39問、
Part 4は10題×3問の計30問になり、
Part 3, 4で合わせて69問になります。
リスニングパートの約7割を占めているので、メインと言えます。
Part 3と4でどちらが大事かと聞かれたら、
私は問題数が多いPart 3が特に大事だと思っています。
難しさは大きくは変わらないと思いますが、
わたしはPart 4の方が、内容もつかみにくいし、
スクリプトが長いことが多くて難しいと思っています。
ただ、Part 4のほうが1人でしゃべっているので、
内容が単純で簡単という方も多いです。

Part 3, 4はいくつか決まりきったパターンがあります。
- 交通機関の遅延で切符を変更する
- 採用に関すること(応募、面接、評価など)
- 商品の割引など
などです。
そして、TOEICの世界では似たような現象が起こります。
- 電車、バス、飛行機などの交通機関は遅延します
- 会社の近くにやたらと新しいレストランがオープンします(なのに閉店はない)
- コピー機はすぐに紙が詰まります
- トラブルが起こると、クーポン(割引券)を渡して幕引きをはかります
このようにお馴染みのパターンがあるので、
会話やスピーチの流れまで
ちゃんと頭に入れておくと良いです。

Part 3, 4で大事なポイントの1つに「先読み」があります。
先読みというのは、
音声を聴く前に設問を読んでおくことです。
この先読みがPart 3, 4の点数に大きく影響します。
先読みの方法は大きく2つあります。
- 設問のみ先読み
設問を先読みして、音声を聴く、
音声が終わったら一気に解答して、
終わり次第、次の問題の先読みを行う - 設問と回答を先読み
設問と回答を先読みして、
音声を聴きながらできるだけ解答する、
終わり次第、次の問題の先読みを行う
どちらの方法でも良いと思いますが、
初心者は設問のみ先読みがおススメです。
解答しながら音声を聴くのは、
かなり耳が慣れていないと大変ですので、
初心者は音声に集中した方が良いと思います。
一方で、上級者は回答まで先読みしたほうが点数が伸びると思います。
理由は、回答まで読んでいることで、
より情報量が多い中で音声を聴けることと、
音声中に答えることで、
内容忘れによる間違いを防げるためです。
内容忘れはもったいない失点だと思うのですが、
会話やスピーチの本題と全然関係のない設問だったりすると、
聴き取れていても、頭から抜けていくものです。
ですので、ある程度耳が慣れて、高得点を狙いたい方は
設問まで読むように切り替えていくのがおススメです。
いずれにしても、この先読みはリズムが大事です。
解答の際に考えすぎると先読みの時間が無くなってしまいますので、
ペースを崩さずに問題を解いていくようにしましょう。

では、次に具体的な対策を紹介します。
Part 3, 4の対策は、模試を使いましょう。
まずは、1回問題を解いた後で、答え合わせを行い、復習をします。
復習の方法は
- スクリプトの精読
- スクリプトの音読
(望ましくはシャドーイング、オーバーラッピング) - 先読みの練習
という流れがおすすめです。
順番に説明をすると、
①スクリプトの精読では、
解答に載っているスクリプトを丁寧に読みましょう。
知らない単語などがあれば覚えます。
スクリプトに載っている単語は文脈で覚えやすいので、
一つ一つつぶしていきましょう。
(単語帳をまだ終わらせていない場合はそちらを優先)
そして、設問の解答根拠がスクリプトのどこにあるのかを
1つ1つチェックして、マーカーでハイライトするなど印をつけましょう。
このトレーニングで正答率がぐっと上がるはずです。
次に②スクリプトの音読です。
これは望ましくはシャドーイングを行ってほしいです。
シャドーイングが苦手な方は、オーバーラッピングでもよいです。
シャドーイングはリスニングのトレーニングに非常に有効です。
一方で、オーバーラッピングはリーディング力が付くと同時に
英語のリズムを体で覚えることができます。
ですが、どちらもかなり負荷のかかるトレーニングではあります。
音声のスピードでスクリプトを読むのは、
いきなりはできません。
ですので、オーバーラッピングやシャドーイングは、
何度も普通にスクリプトを音読をして、
慣れてきた段階で良いと思います。
音読をする際には、話者の気持ちになって、
少しオーバーなくらいに読むと良いと思います。
会話やスピーチの内容をすり込んでいきましょう。
音読の回数に上限はありません、
スラスラ読めるまで、シャドーイングができるまでなど、
自分で目標を決めて反復しましょう。
最後に③先読みの練習です。
先読みの練習のポイントは
音読まで終えて内容が頭に刷り込まれている問題を使うことです。
答えを覚えてしまっていて、効果があるのか?
と思うこともありますが大丈夫です。
分かっている問題を使用することで、
「先読み」のトレーニングに集中ができます。
できるだけ、Part 3の13題、Part 4の10題を通して練習すると良いです。
問題を解くことよりも、
リズムをすり込んでいくことのほうが大事だからです。
この①、②、③までをしっかりと取り組めば、
驚くほど力がつくと思います。

Part 3の最後の3題、Part 4の最後の2題は
図を見ながら音声を聴く問題になります。
グラフィカル問題だけは、必ず回答まで先読みをしましょう。
回答を見てから図をみることで、
図や音声のどこに着目すべきかが見えてきます。
ちゃんと回答を読み、図に集中できれば、
グラフィカル問題は、割と点数が取りやすい印象です。
図のパターンはだいたい決まっていて、
地図、時刻表、天気予報、価格表、売上実績などになります。
ですので、模試などで一通り問題に触れていれば、
それほど怖がる必要はありません。
Part 3, 4まとめ
- 目標を決めて音読を繰り返そう!
- 学習した問題で先読みの練習をしよう!
Part 5(特徴と対策)
ここからリーディングパートになります。
Part 5は短文の穴埋め問題です。
文法知識や単語・熟語知識で解く問題が多いため、
TOEICの文法問題というと基本的にはPart 5を指します。
Part 5は主に
- 文法知識で解く問題
- 単語や熟語、コロケーションなどの知識が問われる問題
- 文脈から解く問題
に分けられます。
1つの問題でこの①、②、③が混合された問題も多いです。
Part 5はとにかくスピードが求められます。
TOEICのリーディングパートは900点台でも
最後まで解けない人が沢山いるほど、時間が足りません。
その中で、Part 6, 7は時間があれば解ける問題が多いのですが、
Part 5は時間をかけてもさほど点数が変わりません。
私のイメージでは、7~8割正解できる人が、
9割以上正解することよりも、
7~8割正解のままで解答のスピードを上げる方が、
楽だし、トータルのスコアにも貢献できると思います。
ですので、ある程度テキストを反復したら、
30問10分くらいの目安で
スピード重視で問題を解くトレーニングをするとよいです。
また、Part 5以外のパートは
模試などを教材に学習すれば良いと思いますが、
Part 5だけは、テキストを1冊取り組むことをおすすめします。
その理由は、
Part 5だけは一通り問題のパターンを網羅して学習した方が良いので、
模試の演習だけでは絶対的に問題数が足りないためです。
1冊で良いと思いますのでテキストを購入して対策をしましょう!

Part 5の対策はテキストを1冊、しっかりと反復することです。
Part 5は単語、熟語、コロケーションなどの
知識を問われる問題がめちゃくちゃ多いです。
こういった問題はしっかりと覚えないといけないです。
問題を解きながら覚える方が効率も良いと思うので、
テキストを使って覚えると良いです。
大体のテキストには、
覚えないといけないフレーズなどが解説されているので、
そこをチェックして覚えていきましょう。
この熟語やコロケーションの問題が
Part 5の勉強をしているのになかなか点数が伸びない鬼門になります。
出てきた問題文を何度も音読して、
粛々と覚えていきましょう。
次に、文法の問題ですが、
これは解説をしっかりと読んで、
理屈を理解することが大事です。
基本のパターンを理解すると応用も効きます。
文法問題は文法の基本的な理解が前提となるので、
中学校レベルの英文法に不安がある方は、
事前にテキストを1冊やりましょう。
仮定法など、中学校レベルを若干超えた問題も普通に出ますので、
高得点を狙っている方はしっかりとした文法書を読んでおくと良いです。
テキストはベストセラーのものならどれでも良いと思います。
以前は問題文全体を読まなくても
空欄の前後を見るだけで解ける問題が多かったのですが、
最近はちゃんと読まないと解けない問題が中心です。
問題の傾向が明らかに変わってきているので、
Part 5対策のテキストを終えたら、
模試などで新しい問題の傾向に慣れていきましょう。
下記に、いくつかおすすめできるテキストを紹介します。
 |  |  |  |
| 1駅1題! TOEIC L&R TEST 文法特急 | TOEIC L&R でる1000問 | 初学向きTOEIC(R) TEST 英文法 出るとこだけ! | 初学向き世界一わかりやすいTOEICテストの授業 |
| 花田徹也 著 | TEX加藤 著 | 小石裕子 著 | 関正生 著 |
| 935円 | 2530円 | 1320円 | 1540円 |
Part 5まとめ
- とにかくスピード重視で問題演習をしよう!
- 熟語、コロケーションはしっかり暗記!
- 文法問題は理屈をしっかりと理解しよう!
Part 6(特徴と対策)
続いてPart 6です。
Part 6は長文の穴埋め問題です。
穴埋めは基本的に、Part 5と同様です。
文法や熟語、コロケーションなどの問題で、
文脈から類推して文を挿入する問題が1つの長文で大抵1題含まれます。
長文の内容はPart 7と基本的に同じですが、
手紙やEメールの割合が高めだと思います。
Part 6はPart 5ほどではないですが、
やっぱり時間を意識してほしくて、
800点以上の高得点を目指す方は1題4問を2分で解き、
合計8分で終わらせるのが理想です。

Part 6の対策は基本的にはPart 5、Part 7と同じです。
Part 5、7のトレーニングをしているうちに、
自然とPart 5も解けるようになってきますので、
Part 6に特化して対策をする必要はさほどないと思います。
問題の解き方としてはPart 5対策が近いと思いますが、
問題演習を行うときの復習は、
私はPart 7と同じ対策を行っていました。
詳しくはPart 7を見て頂きたいのですが、
簡単に説明をすると、
解答根拠を確認した後で、
できるだけ速い速度で5~10回ほど黙読をします。
Part 6は、あまり学習しない方も多いですが、
Part 7が苦手な方にとっては、
文の長さも短いのでいい練習になると思います。
どうしても優先順位で後になりがちですが、
Part 7が苦手な方は参考にしてください。
Part 6まとめ
- 基本的な対策はPart 5、7と同じです!
- できるだけ速く黙読するのがおすすめ。
Part 7(特徴と対策)
Part 7は長文問題です。
長文の内容は、メールや手紙、チラシ、新聞記事などさまざまです。
Part 7の問題はシングルパッセージ(1題で長文が1つ)、
ダブルパッセージ(1題で長文が2つ)、
トリプルパッセージ(1題で長文が3つ)があります。
問題数は
シングルパッセージ:10題29問
ダブルパッセージ:2題10問
トリプルパッセージ:3題15問
です。
問題によって文の長さが全然違います。
また、シングルパッセージは問題によって設問の数もバラバラです。
ダブルパッセージ、トリプルパッセージは
文書自体はさほど長いわけではないですが、
クロスして情報を読み取らなければいけないので、
問題の難しさは格段に上がります。
ダブル・トリプルパッセージのクロス問題と言うのは、
一つの文だけでは解けない問題です。
たとえば、学会発表のタイトルと演者の一覧がある問題には、
別の文で「〇〇について話している発表がとても良かった」
みたいな文が出てきます。
設問は誰の発表がよかったですか?になります。
こういった問題は丁寧に読んでいけば、
明らかに違和感がある文が設問になるのですが、
リーディングパートはとにかく時間との戦いなので、
なかなか注意深く読む余裕がありません。
結果として、余計に問題を解くのに時間がかかってしまいます。

Part 7の対策は、
基本的には模試などを使用すれば良いと思います。
他のパートと同様、1回問題を解いた後で、
答え合わせを行い、復習をします。
復習の方法は、まずはスクリプトの精読です。
丁寧に1文1文を読み、
知らない単語をピックアップして覚えていきましょう。
(単語帳の学習を終えていない方は単語帳を優先してもいいです)
また、設問の根拠となる文を確認して、
丁寧にハイライトするのがおすすめです。
そして、その後はひたすらスクリプトの速読練習をしましょう。
速読練習は音読でも黙読でも良いですが、
私は黙読を行うようにしています。
音読の方が飛ばし読みがないので、
初めは音読をしていましたが、
途中からは、とにかく最速で読めるようにしたいと思い、
黙読をしていました。
基本的には1つのスクリプトを5~10回くらいは読むようにしましょう。
この内容で復習を行うと内容がしっかりと頭に残り、
読むスピードも格段に上がっていきます。
1題復習するのに
30分以上かかることも多いですが、
確実に力につながると思います。
Part 7まとめ
- スクリプトの精読後、速読を繰り返そう!
- 1題あたり5~10回は速読し、読むスピードを上げよう!
さいごに

以上が、わたしのおススメするTOEICの学習方法でした。
ここに書いてある内容に
単語学習を加えたものが私のTOEIC学習になります。
最初に単語、次にPart 5対策を行い、
後は問題集をひたすらやりこんでいました。
私の場合は、模試1回分の学習に30時間以上かかりました。
ちなみに730点のときには
公式問題集1冊を使って模試2セットを行い、
730点⇒775点と伸びました。
そして、その後、
メガ模試を使って、模試6セット分行い
775点⇒900点と伸びました。
自分で力がついているのが実感できたので、
勉強方法は全く変えませんでした。
ですが、点数を見ても分かる通り、
メガ模試6セットをやったときの方が
圧倒的に成果につながっているので、
結局のところ勉強量が効いているのかもしれません。
この学習方法は結構負担が大きいですが、
しっかり力が付くので是非試してみてください。